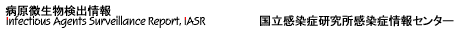|
|
伝染病予防法に基づいた赤痢(アメーバ性を含む)の真症患者,疑似症患者,保菌者の届出患者ならびに死者数の年次推移を図1に示した。比較として赤痢と同じく経口的に感染する疾病である腸チフスの発生状況をあわせて示した。腸チフスが戦後急激に減少したのに対し,赤痢は1960年代中頃まで毎年数万人の患者発生が続いた。その後急速に減少し,1970年代半ば以降1000人前後となったが,ここ数年はやや増加気味であり,まだ完全に制圧されるには至っていない。この種の急性伝染病の減少には,環境改善のみならず,抗生物質の普及が寄与している。赤痢に有効な抗生物質は1950年半ばにかなり普及し,死者数は1960年代に著明に減少した。
これを原因菌の群別にみると(図2),症状が重症になるA群菌がまず激減し,C群とB群がこれに続いて減少したのに対し,D群の減少は1970年代に入ってからで,以前多かったB群に代って1960年代半ば以降D群が主位を占め,現在でもむしろB群より優勢である。このことはD群による赤痢が比較的軽症であるため,正確な臨床診断がされにくいことに関係があると考えられる。
また,1977年以降の患者発生の再増加は海外由来の輸入例の増加を反映している。図3は感染性腸炎研究会で調査された13の都市立伝染病院での患者発生数とこれに占める海外輸入例の割合を示したものであるが,1977年以降ほとんど毎年輸入例が過半数を占めている。1983年には厚生省が全国の赤痢輸入例の調査を実施しているので,この成績ならびに,1983年と84年の地研・保健所における検出報告,感染性腸炎研究会の調査成績を群別にみると,表1のようにA群は少数であるが,71〜100%とほとんどが輸入例で,B群は34〜67%,C群は35〜78%,D群は15〜49%が海外輸入例であった。感染性腸炎研究会の成績は人口100万以上の11都市にある病院の集計なので大都市では輸入例の占める割合が大きいことがわかる。また,D群は国内の集団発生の原因菌となることが多く,集団発生の状況によって年間検出数が大きく変動するが,このなかで輸入例については毎年増加傾向がみられている(図4)。
1984年には航空機乗務員が寄港地で罹患したと推定される事例が11件19例発生し問題になったが,これを含め,輸入例の推定感染国は,毎年インド・ネパール・パキスタンが最も多い。
1984年中に国内集団発生例として地研・保健所から報告された患者数10例以上のものには,地域流行(佐賀県,岐阜県),幼稚園・学校(山形県),保育施設(大阪市),養護施設(広島県),一般家庭での多発(福島県)などがあった。
1984年の分離株について伝染病院でおこなわれた抗生物質感受性試験の成績によると,検査された351株中281株(80%)がクロラムフェニコール,テトラサイクリン,カナマイシン,アンピシリン,ナリジキン酸の5剤のうちいずれかの抗生剤に耐性で,うち174株(62%)が多剤耐性であった。表2に個々の抗生剤に対する耐性頻度を示してある。
図1.赤痢患者数・死者数の年次推移 腸チフスとの比較
図2.菌群別細菌性赤痢患者数
図3.海外由来の細菌性赤痢発生状況
表1.輸入例からの群別赤痢菌検出状況
図4.年次別赤痢菌検出状況(地研・保健所集計)
表2.個々の抗生剤に対する耐性


|