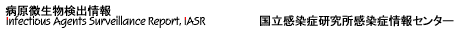|
|
秋田,新潟などでは古くからあったものの,近年ではほとんど幻の病のごとくに思われていた恙虫病が,感染症の変貌が取り沙汰され始めた昭和51年頃から復活の兆しを見せ始め,βラクタム系一辺倒の抗生物質の使用傾向を嘲笑うかのごとく,古来の発生地のみならず予想もされなかった地域をも含めて各地で発生するようになった。しかも症例の多くは,原因不明の熱性疾患として,新しい抗生物質による懸命の治療にもかかわらず重症に経過した後,ようやく本病と診断され,急遽適切な治療に変更して一転快方に向かった症例や,あるいは不幸にして死の転帰をとった後に初めて本病と判明した症例もみられる事態となった。このような事態になる直前の昭和50年には,全国で僅かに15例の発生であったものが,昭和55年には全国13都県で237例が届けられ,その中の3死亡例はいずれも死後の診断例となっている。昭和56年中には,鹿児島県の223名を筆頭に,米軍将兵を含む静岡県の56名,宮崎県26名,新潟県の25名,群馬県20名,秋田県,富山県各18名の他,青森,岩手,山形,福島,東京,長野および熊本県など全国14都県で計409名の発生が届けられている。かくのごとく恙虫病は今や決して限られた地域のみでみられる風土病ではなく,全国いたるところで発生しうる重要な発熱性疾患の1つとなっているのである。
この増多の真因については,本病の場合,病原体であるリケッチと,ベクターである「つつが虫」と,宿主である「ヒト」の三者についての詳細な考察が必要であるが,前二者における真の増多の裏付けは必ずしも明らかではない。しかしながら,宿主に関する増多要因,特に届出数の増多については,重症化傾向に加えて診断法の迅速確実化,あるいは啓蒙運動の普及などが要因となっていることは確かであろう。また,前述の抗生物質の使用傾向の変貌との相関について考察したところ,図1のごとく昭和51年以後のクロラムフェニコールの減退とβラクタム系の急増に,本病発生数の急増が極めて明瞭に相関していた。すなわち最近の抗生物質の使用傾向の変貌が汎用抗生物質の無効な疾患の表面的増加につながっていると考えざるを得ず,これが本病の早期診断,早期治療を現下の急務と考える所以である。
こうしたことから,古来本病の発生地にある我々は,地域医師会報等を通じて臨床診断の普及を図る一方,本病のより早いより正確な病原診断法を開発して適切な治療にあるいは予防対策に資したいと考え研究を続けてきていた。その結果,1980年の発生シーズン以降ようやく初期の目的にかなう方法を確立して県内各医療機関からの迅速診断の依頼に対応できるようになった。すなわち,細胞培養で増植したリケッチアのごく微量を,スライドグラス上にスポットした抗原を用いて,患者血清について間接免疫ペルオキシダーゼ反応を行い,血清入手後数時間以内に抗原型別IgGおよびIgM抗体を分別計測する方法である※。図2に示したごとく,本法によって計測すれば,恙虫病リケッチアに対するIgM抗体は,発病後急速に上昇して5,000〜10,000倍程度に達した後急下降して約半年〜1年以内には消失すること,一方IgG抗体は,IgM抗体に多少遅れて上昇するが,約3週目に最高値に達した後,きわめて緩やかに減少するものの10〜20年の持続が確かめられた。従って本法によれば,まず第一に不明発熱性疾患が恙虫病であるか否か,しかもその感染病原型は何かを単一の血清によって即日診断することがほぼ可能であって,早期に適切な治療に切り換えることによって急速に治癒に導くことができた症例も東北地方では既に数多く経験されている。
また第二に,本法を疫学調査に利用することによって,地域の恙虫病リケッチアの浸淫状況を知ることができるようになった。
古くから本病の診断法として教科書的に用いられているワイルーフェリックス反応への執着は,現段階ではむしろ誤診あるいは早期治療への障害をもたらすものと考えている。また,本病は全国いたるところに存在するものと思われることから,本病の臨床像の要点と臨床的早期診断法および適正抗生物質療法等について図に示し一部の例については表で御参考に供した。
文献※;須藤恒久,間接免疫ペルオキシダーゼ反応による「つつが虫病」の迅速血清診断法,臨床病理,30,10〜17,1982
秋田大学医学部微生物学教室 須藤 恒久
図1.年次別つつが虫病発生数推移・年次別主要抗生物質生産最の推移
図2.つつが虫病の経過(模型)
図3.最近の年次別つつが虫病発生地 秋田県
表.昭和56年におけるつつが虫病患者(56.1〜56.12)(抜粋)(秋田県内居住罹患者)


|