1.A香港型インフルエンザは途絶えないのか
現代人の多くは、抗原性(亜型)の異なる2種類のA型インフルエンザウイルスの同時流行に慣れてしまい、違和感を感じなくなった。
しかし、このように流行が重なるのは1968年の香港かぜ出現以来、A香港型(AH3亜型)ウイルスが40年経っても途絶えずに流行を続けているからではないだろうか。前世紀のパンデミックのうち、スペインかぜ(1918年〜)はアジアかぜ(1957年〜)の出現により、アジアかぜは香港かぜの出現により姿を消した。一方、AH3亜型ウイルスは1977年にソ連かぜの世界的流行が起きても(パンデミックではないが)、さらには2009年に豚由来AH1 ウイルス(AH1pdm09)1) によるパンデミックが起きても、姿を消さず流行を続けている。
2.A香港型インフルエンザの年度別発生
当科では1998年7月以降、小児科定点としてインフルエンザのサーベイランスを続けてきた2,3) 。インフルエンザ様患児のうち、入院治療や輸液治療を要する患児をウイルス分離対象とし(AH1pdm09の流行初期のみ全数把握態勢のため軽症例を含む)、これまでに93例の患児からAH3亜型ウイルスが検出された。ウイルス分離は主にMDCK細胞を用いて行われ、一部がRT-PCRやリアルタイムPCRによった(奈良県保健環境研究センター)。
1小児科定点の成績であるが、年度別に発生をみると、AH3亜型ウイルスは、AH1pdm09が猛威を振るった2009年度を除いて、毎年検出されている(1998年度の検出数が突出しているのはA/Sydney/5/97類似株の流行によると考えられる)(図1)。この間、Aソ連型やB型には全く検出されない非流行年(それぞれ3年連続を含む)がみられた2,3) (データ省略)。
3.A香港型インフルエンザ患児の年齢分布
93例の年齢分布を示した(図2)。乳幼児の占める割合が高く、5歳未満が72%(67例)を占めている(図2)。
4.インフルエンザ患児の罹患年齢の亜型別比較
ウイルス分離対象に軽症例を含まなかったことで乳幼児の比率が高くなった可能性も考えられる。そこで、罹患年齢の亜型別比較も行った。2群間の差の検定にはMann-WhitneyのU検定を用いた。その結果、A香港型インフルエンザ患児の年齢(3.8±3.4歳)は、Aソ連型患児(5.2± 3.4歳)、B型患児(4.9±3.1歳)、AH1pdm09患児(7.1±3.7歳)に比べて有意に低いことが判明した(図3)。
5.考 察
A香港型ウイルスは長期にわたって毎年のように流行を続けてきた。したがって、15歳までの小児年齢のうち年長児では過去に同ウイルスに曝露された児が多いであろう。抗体保有率が年長児で上昇し、低年齢児(特に5歳未満)に罹患が集中するのではないかと考えられる3) 。
今回の成績は1小児科定点の成績であるが、最近、発表された2010/11シーズン前のインフルエンザ抗体保有状況4) (国立感染症研究所)をみると、AH3亜型ウイルスに対して、0〜4歳群を除くすべての年齢層で中等度以上の抗体保有率を示す成績であった。
A香港型インフルエンザの小児の罹患が低年齢児に多い傾向にあることは定着しつつあるようであり、今後も警戒が必要である3) 。インフルエンザ合併症の頻度を亜型別にみると、熱性けいれんや脳症はA香港型で最も頻度が高い3) 。
2011年11月、米国アイオワ州で豚との接触の確認されない小児3例に豚由来AH3亜型ウイルスの感染が確認された5) 。
今後もAH3亜型ウイルスの動向が注目され、サーベイランスを続けることは重要であろう。
インフルエンザウイルスの検出および抗原解析はすべて奈良県保健環境研究センターウイルスチームによるものであり、深謝する。
参考文献
1) IASR 30: 255-256, 2009
2) 松永健司,他,小児科臨床 61: 1691-1694, 2008
3) 松永健司,他,小児科臨床 62: 1105-1110, 2009
4) IASR 32: 323-326, 2011
5) CDC, MMWR 60: 1615-1617, 2011
済生会御所病院小児科 松永健司
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

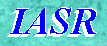
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る