類鼻疽(メリオイドーシス、melioidosis)は、グラム陰性桿菌であるBurkholderia pseudomallei による人獣共通感染症で、東南アジア、北部オーストラリアなどの熱帯、亜熱帯地域に多く発生する風土病である。本邦では国内発生例はないが、現在までに輸入感染症として8例の報告がある。今回我々は、ベトナムからの帰国後、皮膚、肺、脾、腎、骨髄の多臓器に病変を認めた類鼻疽の1例を経験したので報告する。
症例:69歳、男性
主訴:発熱
既往歴:50歳 糖尿病(経口糖尿病薬内服中)、急性心筋梗塞
現病歴:約20年前より仕事のためベトナムへの渡航を繰り返していた。2009年8月に約3週間ベトナムに滞在し、帰国した直後より39℃台の発熱を認めた。糖尿病で通院中の近医を受診し、胸部X線写真、CT(図1)にて右上葉に空洞を伴う浸潤影を認め、肺炎と診断された。1カ月間levofloxacin 500mg/日を投与され肺炎は改善した。その後も微熱が続き、12月下旬より左腰部の皮下に増大傾向のある柔らかい腫瘤を自覚していた。2010年1月中旬より再度39℃台の発熱を認め当科に紹介入院となった。
入院時身体所見:意識清明、体温39.0℃、血圧124/64mmHg、脈拍110回/分、SpO2 99%(室内気)、右前胸部でcoarse cracklesを聴取、心音純。腹部に異常所見なし。左腰部に約10cmの皮下膿瘍を認める。右足関節に発赤、熱感、圧痛を伴う腫脹を認める。
入院時血液検査:WBC 7,700/μl、RBC 409万/μl、Hb 11.9g/dl、Plt 5.3万/μl、TP 7.4g/dl、Alb 2.9g/dl、BUN 19.5mg/dl、Cre 1.0mg/dl、Na 123 mEq/l、K 4.8 mEq/l、GOT 106 IU/l、GPT 52 IU/l、LDH 244 IU/l、ALP 1,213 IU/l、γGTP 269 IU/l、Glu 264 mg/dl、CRP 22.0 mg/dl、HbA1c 10.5%、PT 16.6秒、APTT 60.0秒、FDP 25.2μg/ml。
胸腹部造影CT:両側肺野末梢に径2.5cm大までの結節性浸潤影を数個認める。軽度脾腫あり。脾臓、両側腎に造影効果のない低吸収域が多発。
足関節MRI:右脛骨骨幹から遠位骨幹端にT1強調像で低信号、T2強調像で高信号を呈する異常域が多発。
臨床経過:前述した血液検査および画像所見より皮下膿瘍、敗血症性肺塞栓、脾膿瘍、腎膿瘍、骨髄炎および敗血症、DIC診断し、直ちにmeropenem 1.5g/日、gentamicin 240mg/日、clindamycin 1,200mg/日、メシル酸ナファモスタット 200mg/日、免疫グロブリン 5,000mg/日の投与を開始した。入院時に施行した左腰部皮下膿瘍の切開ドレナージにて採取した膿、および血液培養の塗抹標本にて両極染性を示すグラム陰性桿菌を認め(図2)、菌の生化学的性質からB. pseudomallei が強く疑われたため、国立感染症研究所へ検体を送付した。同・細菌第二部における検査で、核酸検出法(LAMP法)陽性、培養法によるコロニーの確認、アラビノース分解能(−)であったことから、B. pseudomallei と同定した。参考情報として、B. pseudomallei に対するモノクローナル抗体凝集反応は陽性であった。
薬剤感受性検査にて多剤耐性を示したが、meropenemには感受性があったため、抗菌薬は同薬剤を2.0g/日に増量し、その他は終了した。解熱するまでに約1週間を要したが、敗血症性ショックには至ることなく経過している。現在第31病日で血液検査上炎症反応の改善は続いているが、画像上脾膿瘍、右脛骨骨髄炎は改善に乏しく、長期の抗菌薬継続投与を予定している。
考察:類鼻疽はB. pseudomallei による人獣共通感染症である。本菌は主に北緯20度から南緯20度の熱帯、亜熱帯地域の土壌や田圃等の水の流れがよどんだところなどから検出され、日本では確認されていない。類鼻疽は東南アジア(特にタイ東北部)や北部オーストラリアに多いが、中国南部やインド、パプアニューギニア、ニューカレドニアなどでの報告例もあり、海外渡航歴がある場合には留意する必要がある。感染経路としては経皮感染、経気道的感染、経口感染があり、損傷皮膚からの経皮感染が最も多いとされている。基礎疾患として特に糖尿病が多く、約半数に上る。重症化することも多く、皮膚などの局所感染巣から菌血症を生じ、血行性に肺炎や肝臓、脾臓、腎臓、前立腺などの全身臓器に膿瘍を形成、骨髄炎や関節炎を生じる症例もある。敗血症性ショックを伴う場合には致死率も高い。
診断は培養による分離・同定が基本だが、グラム染色にて両極染性を示すこと、また、コロニーの特徴として培養数日後に多数の放射状の皺を生じることが診断の参考になる。
本菌はペニシリン、第1・2世代セフェム、アミノグリコシドなど種々の抗菌薬に耐性を示し、さらにマクロファージ内などで何年間も生存可能な強毒性の細胞内寄生菌であるため、治療後の再燃、再発が多い。初期治療としては現在、ceftazidime±trimethoprim-sulfamethoxazole、あるいはmeropenem、imipenemの投与が基本で、軽症の場合でも最低2週間の投与が推奨されている。
再燃、再発を予防するために初期治療後には3〜6カ月ほどの維持治療を行うことが重要であり、trimethoprim-sulfamethoxazoleを中心とした治療が行われているが、コンプライアンスの悪い症例では特に再発が多い。
日本国内においても東南アジア方面などへの海外渡航者、あるいは海外からの移住者などが近年増加しており、本疾患の存在を念頭において診療を行うことが重要である。
平塚共済病院呼吸器科 倉田季代子
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

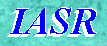
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る