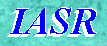
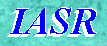
The Topic of This Month Vol.31 No.1(No.359)
カンピロバクター腸炎の起因菌は主にCampylobacter jejuni であるが、まれにC. coli も報告されている。わが国におけるカンピロバクター腸炎の発生状況は、(1)食品衛生法に基づく食中毒統計、(2)地方衛生研究所(地研)・保健所での病原菌検出報告(病原微生物検出情報)、(3)都市立感染症指定医療機関(13大都市16病院)に入院した感染性腸炎患者調査報告(感染性腸炎研究会)により把握されている。また、衛生微生物技術協議会レファレンス委員会カンピロバクターレファレンスセンターでは、カンピロバクター菌株を収集し、血清型別と薬剤感受性試験を実施している。本特集はこれらの資料をもとに最近4年間の全国の状況について述べる(2005年までの発生状況はIASR 14: 143-144, 1993、16: 149-150, 1995、20: 107-108,1999 & 27: 167-168, 2006を参照)。
食中毒統計:病因物質別食中毒事件数をみると、1999年まではカンピロバクターよりもサルモネラと腸炎ビブリオの方が多かったが、2000年以降サルモネラと腸炎ビブリオは大きく減少した。これに対し、カンピロバクターは目立った減少はみられない(表1)。1997年以降、一部自治体で患者数1人の食中毒事例も届け出るようになった(本号14ページ)ことが影響して、カンピロバクター食中毒事件数では1人事例の占める割合が高いが、2人以上事例も年々増加している(本号4ページ)。
カンピロバクター食中毒患者数は2002年に2,000人を超え、2005年には3,439人を記録し、その後もノロウイルスに次いでサルモネラとほぼ同数で推移している(表1)。
病原菌検出報告:年別カンピロバクター検出報告数も2003年以降増加して1,100〜1,200前後で推移している(表2)。C. jejuni が90%以上を占め、C. coli は少なかった。また、従来同様輸入例は非常に少ない。月別カンピロバクター検出報告数は、従来同様5〜7月にピークがみられた(図1)。
2006〜2009年に地研・保健所から報告されたカンピロバクター食中毒集団発生は323件であった(表3)。夏季にピークのみられるサルモネラや腸炎ビブリオによる食中毒よりも早く5〜6月にピークがみられ、冬季にも発生している。発生規模別では、患者数100人以上の集団発生は1件のみで(本号10ページ)、2005年以前の報告より少なかった。50〜99人が8件(本号7ページ、9ページ&13ページおよびIASR 28:115-116, 2007)、10〜49人が103件、2〜9人が125件であった(表3)。推定原因食品が記載されていた中では、肉類が最も多かった(表3)。原因となる肉類の大半は鶏肉およびその内臓であるが、牛レバーなどその他の動物の内臓の生食によるものもみられる(IASR 27:266-267, 2006)。
2006〜2009年に地研・保健所から報告された食品検査結果では、鶏肉の75%、その他の食肉の75%からC. jejuni またはC. coli が分離された(表4)。
入院例:2006〜2008年にカンピロバクター腸炎で入院した患者310例の年齢分布をみると(表5)、2005年までの報告とほぼ同様に、0〜9歳が25%、10〜19歳が23%、20〜29歳が27%で、30歳以上は少なかったが、60歳以上の割合(11%)がやや増加していた(2003〜2005年は5%)。また、20〜39歳では、その23%が海外で感染した輸入例であった。性別では男性の方が多かった。
分離菌株の血清型別:カンピロバクターレファレンスセンターはLiorシステムによるC. jejuni の血清型別を行っている。2005〜2008年に散発下痢症由来C. jejuni 2,504株が型別に供された。1,610株が単独血清型に型別され、LIO4型が524株と最も多く、次いでLIO10型が122株であった(本号15ページ)。
薬剤感受性:上記の2005〜2008年の散発下痢症由来C. jejuni 2,366株では、第一選択薬であるエリスロマイシン(EM)耐性株は0.7%と非常に少なかったが、テトラサイクリン(TC)耐性が35%、フルオロキノロン系抗菌薬(FQ)耐性が33%であった。これに対し、C. coli 75株ではEM耐性が21%と多く、TC耐性が75%、FQ耐性が63%であった(本号15ページ)。
一方、家畜から分離されるカンピロバクターは牛および鶏からはC. jejuni 、豚からはC. coli が主で、C. jejuni ではEM耐性が認められないが、C. coli では認められている(本号17ページ)。
問題点と対策:カンピロバクター腸炎の多くは本菌に汚染された肉類を生食あるいは加熱不十分で喫食した場合に起きている(本号7ページ、10ページ、11ページ & 13ページ)。食肉のカンピロバクター汚染実態調査によれば、市販の鶏肉は高率に汚染されており、健康な牛の肝臓は内部まで汚染されていた(本号4ページ)。
しかし、カンピロバクター食中毒では、原因食品が特定できない事例が非常に多い。原因施設として最も多い飲食店などでは、提供された食品が保存されていないことが多いため、検査が実施できない。また、本菌により食中毒を起こす感染菌量が数100〜数1,000個と非常に少ないため、低濃度汚染の菌を食品から分離することが技術的に難しい。また、冷凍により損傷を受けた少量の菌を分離することも困難である。今後、これらの課題を解決するための検査法の改良が必要であろう。
一方、家庭で喫食した場合など、疫学調査が困難な場合には、原因食品不明のまま「有症苦情」で終わる事例も少なくないと考えられる。実際のカンピロバクター腸炎患者数は、現在の報告数よりはるかに多い年間約150万人と推定されている(本号5ページ)。また、カンピロバクターは毎年人口10万人に1〜2人の発生がある神経疾患のギランバレー症候群に関係しているとされている。
内閣府食品安全委員会微生物・ウイルス専門調査会では、2009年6月に鶏肉中のC. jejuni/coli についてリスク評価を行った。感染確率を定量的に評価した結果によると、鶏肉を生食する人では大きくリスクが増えること、食鳥処理場における交差汚染を避けることと農場汚染率を下げることの組み合わせがリスクの低減に最も効果が大きいことが示された(本号5ページ)。
カンピロバクター腸炎予防の一般的注意としては、肉類の生食を避け、十分な加熱調理を行い、まな板等の調理器具や手指を介した他の食品(特に生野菜など加熱せずに摂取する食品)への二次汚染に気を付けることが必要である。食肉の生食という食習慣は、腸管出血性大腸菌やE型肝炎ウイルスなどへの感染の危険性もあるため、厚生労働省(「カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)」http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/campylo/index.html)や東京都(「ちょっと待って!お肉の生食」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/anzen/anzen_info/nama/index.html)などの多くの自治体が消費者への普及啓発を行っているが、まだ十分に功を奏しているとは言えないのが実情であろう。
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)
