1.はじめに
RSウイルス(RSV)は、一本鎖(−)RNAウイルスでエンベロープを有し、パラミクソウイルスに属しているが、血球凝集やノイラミニダーゼ活性を示さない。1956年に動物より、翌年にはヒトからも分離された。乳児の半数以上が1歳までに、ほぼ 100%が2歳までに感染を受けるが、その後も一生の間再感染を繰り返す。血清型は一つであるが大きくグループA、Bに分けられ、さらに様々な遺伝子亜型が存在している。
2.臨床徴候
RSV感染症の臨床病型の基準を表に示す。感染が上気道(鼻粘膜)から経気道的にどこまで波及するかによって、急性上気道炎、喉頭気管気管支炎、細気管支炎、そして肺炎と病像が変わる。初感染においては30%程度が下気道炎に至り、1〜3%が重症化し入院治療を要する。わが国では毎年2万人程度の入院があると推定される。
咳嗽、鼻汁などの上気道症状が2〜3日続いた後、感染が下気道、とくに細気管支に及んだ場合には特徴的な病型である細気管支炎となる。炎症性浮腫と分泌物、脱落上皮により細気管支が狭隘となるに従い、呼気性喘鳴、多呼吸、陥没呼吸などを呈する。胸部X線像では含気量の増加による、び漫性の肺気腫像がみられる。血液ガス分析では、低酸素、高炭酸ガス血症をしばしば認める。心肺に基礎疾患を有する児においては、しばしば遷延化、重症化する。喀痰の貯留により無気肺をおこしやすい(図)。
救急医療における重要な病態として、RSV感染による無呼吸がある。生後1カ月未満の新生児に認められることが多い。RSV感染が下気道炎まで進行し、呼吸困難とともに無呼吸を呈する場合もあるが、咳嗽、鼻汁だけの感染の初期に、自宅で夜間睡眠中に頑固な無呼吸を呈することも多い。この際には、突然死の原因ともなりうる。その機序として、未熟児・新生児にみられる呼吸中枢の未熟性が背景にあるが、それに加え咽喉頭に分泌物が貯留することにより生じる反射による無呼吸、さらに増加した分泌物による単純な閉塞性無呼吸も考えられている。
頻度は高くないが、胸腔内圧の上昇を伴うRSV下気道炎の合併症としてADH分泌異常症候群(syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: SIADH)がある。細気管支炎の場合には、程度の差はあれSIADHの病態が生じ、低ナトリウム血症の傾向が見られるので、補液の内容と速度の選択には注意が必要である。
3.診断のための臨床検査
RSVにおいては不顕性感染、潜伏感染が無いことから、急性の呼吸器症状を呈する患者よりRSVが検出された場合、RSV感染症と診断しうる。他の呼吸器ウイルス感染でも同様な症状を呈しうるので、確定診断にはウイルス学的検査が不可欠である。ウイルスは初感染の場合、発症後1週間〜10日間は、気道分泌物中に存在すると考えられる。検体としてはいずれも鼻咽頭分泌物が最良であるが、鼻汁においてもほぼ良好な結果が得られる。
ウイルス分離は、基本的で重要な病原診断であるが、RSVの場合、凍結検体からの分離率は低下し、冷蔵保存でも不安定であるので、検体の採取後は速やかに細胞に接種する必要がある。HEp-2細胞を用いるのが最良である。分離陽性の場合、2〜5日で特徴的な合胞体形成を伴う細胞変性効果が現れる。
免疫クロマト法にてワンステップの10分程でRSV抗原を検出する迅速診断法が普及している。特別な器具を必要とせずベッドサイド、一般外来での使用が可能である。2006(平成18)年4月より3歳未満という年齢制限が取れているが、保険適応は入院のみとなっている。ウイルス分離にそれほど劣らない感度を有し、特異性もほぼ 100%である。早期の治療方針の決定、さらに有効な院内感染対策の構築が可能となった。
PCR法にてウイルス遺伝子そのもの、あるいはmRNAを検出することが研究室レベルで行われている。極めて感度・精度が高く、凍結保存検体も使用できる。一方、施設、設備を必要とし、手技がやや複雑で経費もかかる。陽性の場合に診断的意義は高いが、ウイルス分離や迅速抗原検査などで、ほぼ100%病原診断が可能であることから、この遺伝子診断法は、亜型の同定やウイルスの伝搬、変異の様子を探るなど研究面での利用がなされている。
4.治療
気管支炎、細気管支炎や肺炎に対しては、適切な輸液、気道分泌物の機械的な除去、去痰剤の投与、適切な体位、ヘッドボックスなどを用い加湿された酸素の投与などの対症療法が基本となる。呼吸不全が進行する重症例においては、人工換気の適応となるが、数日で離脱できることが多い。気管支拡張作用を期待してのキサンチン製剤の効果については、一定した見解が得られていないが、無呼吸に対しては治療と予防に効果的である。ステロイド剤は、吸入、静脈注射のいずれの場合でも、その効果は不明であるとされる。
5.予防
米国でヒト化抗RSV-F蛋白単クローン抗体(パリビズマブ)が開発されたが、RSV流行期を通して月1回の筋注投与がRSV感染症の重症化を防ぎ、入院率を有意に下げることが証明された。わが国でもRSV感染流行初期において(1)在胎期間28週以下の早産で、12カ月齢以下の新生児および乳児、(2)在胎期間29週〜35週の早産で、6カ月齢以下の新生児および乳児、(3)過去6カ月以内に気管支肺異形成症(BPD)の治療を受けた24カ月齢以下の新生児、乳児および幼児、(4)24カ月齢以下の血行動態に異常のある先天性心疾患(CHD)の新生児、乳児および幼児、などに対して保険収載の上での予防投与が開始され、ある程度の効果が確認されている。
札幌医科大学医学部小児科学講座 堤 裕幸
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

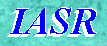
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る