感染研では従来から、海外で流行中の狂犬病の国内発生に備えて、ウイルス第一部、獣医科学部、感染病理部および感染症情報センターが中心となって、(1)狂犬病に関する科学情報の収集・分析、(2)ヒトおよび動物の狂犬病疑い症例に対する迅速かつ確実な病原体診断の準備、(3)予防対策や流行状況等の啓発普及等、事前の対応に努めてきた。筆者は、今回個別に発生した2症例の対応において、後述する感染研の狂犬病疑い症例対応チーム(仮称)の一員として、所内関係部および厚生労働本省等との連絡調整に係わったことから、本稿ではその感染研の対応概要について紹介する。
1.疑い症例の第一報とその検討
京都市、横浜市のいずれの症例も、病院主治医から感染研への電話連絡が、狂犬病疑い症例の発生を伝える第一報となった[第一報の連絡日はそれぞれ2006(平成18)年11月15日、同じく11月20日]。これを踏まえ感染研では、直ちにウイルス第一部および獣医科学部の関係者が所内横断的に参集して狂犬病疑い症例対応チーム(仮称)を結成し、両症例に対応することとなった(本号10ページ参照)。チームでは主治医と連絡を取り、疑い症例の臨床・疫学情報を確認し、特に渡航歴(狂犬病流行地のフィリピン)、動物咬傷歴(現地のイヌに咬まれる)、経過(咬傷後約3カ月で発症)、症状(恐水症、恐風症状、他の神経症状、および咬傷部位の痒みしびれ等)から、狂犬病の発症を強く疑うに至った。参考まで2症例の対応の時間的経過を図1に示した。
2.検体採取等の準備と関係者への連絡
狂犬病の発症が疑われることを踏まえ、早急に生前の病原体診断を試みるために、感染病理部も加わって、診断方法、必要となる検体材料等を検討し、主治医と連絡調整の上、感染研職員を現地病院に派遣して検体を受領することとなった。検体材料は、唾液、尿、血液、後頭部の毛根皮下組織とし、これを用いて当面、遺伝子診断(PCR およびリアルタイムPCR をそれぞれ別検査室で実施)、抗原診断(免疫組織化学法)を行うこととし、これに必要な所内検査室での病原体診断の準備を進めた。また、上述の技術的な検討対応と並行して、当該事例の発生等の情報について疫学調査を担当する感染症情報センターと共有するとともに、本省結核感染症課と協議し、生前の病原体診断で狂犬病であることが判明した場合の対応について検討・準備を開始した。
3.病原体診断の結果とそれを踏まえた対応
病原体診断の結果、2症例ともPCR法(2種いずれとも)により唾液から狂犬病ウイルスの遺伝子を検出し、この検出遺伝子のシーケンスを決定してフィリピン株との高い相同性を確認した(本号3ページ参照)。さらに京都事例では免疫組織化学法により後項部毛根部神経組織内のウイルス抗原を確認した(本号13ページ参照)。感染研では、この病原体診断結果をそれぞれ主治医に連絡するとともに、本省結核感染症課に報告し、狂犬病発生(およびそれに続く2例目)に必要な対応について協議した。それぞれの主治医は病原体診断結果を踏まえて狂犬病と診断し、地元自治体に感染症法に基づく狂犬病患者発生届出を行った。地元自治体および厚労省では36年ぶりとなる狂犬病の2例の発生を踏まえ、プレス対応を含めた情報提供、相談等の行政対応を実施した。さらに患者の死後、それぞれの病院では遺族の同意を得て剖検が行われ、感染病理部が協力して病理学的な検討が行われた(本号13ページ参照)。
4.本事例で得られた知見および経験の検証と共有
感染研では2症例の対応が一段落した後、そこで得られた狂犬病に関する科学的知見と、疑い症例の発生から病原体診断の実施および行政対応に至る経過について、検証と共有化を図ることを目的にセミナー等を開催した。セミナーは「狂犬病患者の発生を踏まえて−京都と横浜の発生事例の検証から−」と題するもので、2006(平成18)年12月22日、感染研において公衆衛生、医療等の担当者向けに行われた。本セミナーには全国より約240名(35都道府県 110名、48市区73名、9大学11名、5研究所7名、3病院5名、その他約30名)の出席があった。本セミナーのプログラムは図2のとおりである(講演のスライド原稿をまとめた小冊子を現在作成中)。また、2007(平成19)年2月15日には、平成18年度の「希少感染症診断技術研修会」において、獣医科学部より狂犬病の生前診断を中心に狂犬病の検査法の解説と、今後の発生に備えた「感染研への狂犬病疑い症例連絡メモ」および自治体からの行政検査連絡先が紹介された(本号10ページ参照)。
今回の国内における2例の狂犬病症例の発生については、主治医が狂犬病を疑って感染研に一報したこと、病原体診断の結果が生前に得られたこと、中央および地方の行政対応が円滑だったこと等から、幸いにも大きな混乱を生じることなく対応することができた。狂犬病のような、わが国では発生が極めて稀な感染症については、対応にあたる者の入念な事前準備と発生時の関係者間の密接な連携協力が欠かせないことを、今回の一連の対応を通じて改めて認識したところである。 終わりに、今後の貴重な資料となる本事例は、各現場での多大な努力と、2名の尊い生命の犠牲の上にあることを思い起こし、今後の対応に活かしていくことが望まれる。
国立感染症研究所国際協力室 中嶋建介
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

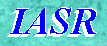
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る