わが国では1950(昭和25)年に制定された「狂犬病予防法」によりイヌの狂犬病対策が強力に推進されて、国内では1956(昭和31)年のヒト1例、イヌ6頭、1957(昭和32)年のネコ1頭を最後に狂犬病の発生報告がなくなった。しかしながら、近隣のアジア諸国では現在もイヌを中心とした狂犬病が流行しており、公衆衛生上の大きな課題となっている。
2006(平成18)年11月に、ヒトの輸入狂犬病が京都と横浜で続けて2例発生した(本号3ぺージ&4ページ参照)。これは、1970(昭和45)年にネパールでイヌに咬まれた青年が帰国後に狂犬病を発症して死亡してから実に36年ぶりの症例である。この2例の輸入狂犬病から、発生が希少ではあるが、病態が重篤で社会不安を引き起こしやすい輸入感染症の対策には「侵入リスクの低減」に加えて「発生に備えた対策」も大変重要であることが改めて理解された。
2005(平成17)年度の日本人海外渡航者数はおよそ1,700万人といわれ、このうちアジアへの渡航者は、中国に250万人、タイに100万人、フィリピンに40万人と報告されている。今後も、海外渡航者に対する適切な狂犬病の情報提供と継続的な危機意識の啓発が行われることが望まれるが、同時に、希少な事例ではあるが、狂犬病の疑われる患者を見逃さないように臨床鑑別が十分になされて、正しい疫学情報の収集と分析のもと、疑いが濃厚となった患者に対する迅速、正確かつ慎重な病原体診断と適切な行政の初期対応が行えるようにしておくことも必要である。
以下にヒトの狂犬病疑い患者に対する生前診断に必要なポイントについて示す。
生前診断の前に(疑い患者についての相談)
現在、国立感染症研究所(感染研)では、フィリピンからの輸入狂犬病症例の経験を踏まえて、狂犬病疑い症例対応チーム(ウイルス第一部、獣医科学部、感染病理部)による狂犬病の病原体診断(行政検査)が可能である(図1)。狂犬病の行政検査は、まず初めに自治体から結核感染症課に連絡が入って、その後、結核感染症課から感染研に依頼されることとなっている。なお、狂犬病疑い症例について感染研に連絡を行う場合には、疑い事例の検討と同時に行政検査対応が迅速、適切に行い得るように、必要な情報について「連絡メモ」(図2)として参考に示しておく。
狂犬病の実験室内診断
狂犬病は、ヒトも動物(イヌ等)も感染して発症したらほぼ100%死亡する動物由来感染症(zoonosis)である。アジアでヒトへの感染リスクが最も高い感染源動物はイヌである。狂犬病の発生している国で狂犬病の疑われるイヌに咬傷を受けた場合には、咬傷犬を捕獲、観察(10日間)して狂犬病が疑われた場合に解剖を行い、狂犬病検査が確実にできる脳組織(延髄、橋、視床、小脳、海馬)を利用した直接蛍光抗体法やRT-PCR法によって病原体診断が行われる(病原体検出マニュアルを参照:http://www.nih.go.jp/niid/reference/index.html)。一方、狂犬病の疑われた患者では、脳を取り出して病原体診断を行うことができないため、生検材料による生前診断を行うことになる。
以下、生前診断のポイントと課題について述べる。
狂犬病の原因ウイルスである狂犬病ウイルスは非常に神経親和性が強いウイルスであり、感染後の長い潜伏期(1カ月〜3カ月)が大きな特徴である。狂犬病ウイルスに感染したヒトも動物も、発症するまでの長い潜伏期間中にウイルス血症はみられず、狂犬病を発症するまでウイルスを検出・分離することもできない。同様に発症するまで血清中にウイルスに対する中和抗体をも検出することができない。また、曝露前および曝露後のワクチン接種を行ったヒトでは抗体価の上昇が見られるため、狂犬病の血清診断的価値は低いとされている。
以下、「検体の採材」、「検体の移送」、「生検を利用した病原体診断」について述べる。
生検を利用した病原体診断
検体の採取:狂犬病が疑われた患者の病原体診断は、「唾液」、「脳脊髄液」、「うなじの毛根部組織」で行う。唾液と脳脊髄液は、1回の検査に500ulを使用するため、再検査を考慮して1ml〜2ml以上の採取が望まれる。うなじの毛根部組織は、後頭部うなじの生え際について直径5〜6mm以上の範囲で10本以上の毛根部を含むように皮下組織ごとバイオプシを行う。組織は可能であれば2カ所採材して1つを中性緩衝ホルマリンに入れて病理組織検索用とし、1つを病原体検出用とする。「血清」については、500ul以上あれば中和抗体の検査が可能である。
検体の保存:いずれの検体も採材後は速やかに冷蔵状態として検査施設に移送する。検査が当日行えない場合には、−20℃以下で冷凍保存を行った後に、速やかにドライアイス等で冷凍状態のまま移送を行う。長期間保存する場合には−70℃以下が望ましい。ただし、ホルマリン固定されたうなじの毛根部組織については冷蔵状態で保存を行い、冷蔵もしくは室温にて移送を行う。
検体の移送:検体は液漏れのしない一次容器(スクリューキャップチューブ等)に入れてチューブの口をパラフィルム等で固定する。一次容器と二次容器の間には、内容物をすべて吸収するために十分な量の吸収材を入れる。移送は、二次容器を三次容器にいれて行う。移送に際しては、送付検体に「送付病院名」、「患者を特定できる記号等」、「日付」、「採取検体名」を明記すると同時に、「送付病院と担当医師の名前・連絡先」、「患者の記号等」、「日付」、「採取検体名および患者の臨床症状と事例の疫学的背景等(図2:連絡メモ等を参考に)」を明記した記録用紙も作成して送る。
病原体診断:「唾液」、「脳脊髄液」についてはRT-PCR法による遺伝子検出が行われる。また、「うなじの毛根部組織」については、RT-PCR法による遺伝子検出と免疫組織化学法による抗原検出が可能である。RT-PCR法と免疫組織化学法により狂犬病ウイルスに特異的な遺伝子や抗原が検出された時点で狂犬病陽性となるが、発生の稀な感染症であることや、感染経路の特定により輸入感染症の是非を明らかにするために、RT-PCR法によって検出された遺伝子の塩基配列について解読を行って最終的に狂犬病であることを確定する。
なお、採材された生検材料から狂犬病ウイルスの遺伝子や抗原は検出されなかったが、患者の臨床症状等から狂犬病が強く疑われる場合には、数日後に生検を行うと同時に、生検材料を乳飲みマウスや培養細胞に接種してウイルスの分離を試みる。
狂犬病の生前診断では、検体の採取時期や患者の病態等により検査材料が十分採取できない場合や、採取した検体からウイルスを検出できない時期がある(表1、表2)。したがって、狂犬病の疑われる患者の生前診断では、病原体診断が陰性の場合でも狂犬病を否定することはできない。このため、数日の間隔で生検材料を採材して病原体診断を繰り返す必要がある。海外の事例では、死後の剖検により採材された脳組織や唾液腺について病原体診断を行って、初めて狂犬病と確定された事例が幾例もある。表3に生前診断の課題について主なものを列記しておく。
剖検による病理診断(病原体診断)
狂犬病の生前診断で狂犬病と診断ができないまま患者が死亡した場合には、剖検による病理診断を行うことが望まれる。狂犬病で死亡した患者の剖検では、肉眼所見で狂犬病を疑うような著変が認められないため、狂犬病ウイルスが増殖している脳、唾液腺等の神経組織を採材してウイルス分離、ウイルスの遺伝子および抗原検出による病原体診断を行う。狂犬病は発症するとほぼ 100%死亡する動物由来感染症であり、死後の剖検による病理診断を行って狂犬病の診断がすべて終了することになる。
病原体診断により狂犬病が確定された場合には、患者と濃厚な接触のあった親族や医療関係者等へのPEPの継続を行う必要がある。また、患者が国内で咬傷を受けて発病したと判断される場合には、国内で感染源となった動物に対する対策が必要となる。
わが国の狂犬病対策では、海外で感染して帰国したヒトとともに、海外から持ち込まれる動物に対する対策が大変重要である。しかしながら、海外から国内に持ち込まれるすべての哺乳類を完全に把握することは現時点では極めて困難であり、世界における狂犬病の発生状況を考えると、狂犬病が日本に侵入するリスクは決して無くなることがないと思われる。したがって、イヌ等の輸入検疫、動物の輸入届出、侵入動物の監視、飼育犬の登録と予防接種、放浪犬の捕獲と抑留等による狂犬病の侵入・発生リスク低減とともに、国内で狂犬病が疑われた、もしくは発生した場合に備えた対策(行政関連機関等における対応マニュアルや検査システム等の事前準備)と、地域ごとのリスク調査が今後も重要である。
2006(平成18)年11月に、36年ぶりのヒトの輸入狂犬病を続けて2例経験して、発生が希少ではあるが、病態が重篤で社会不安を引き起こしやすい狂犬病では「発生に備えた対策」の必要性が改めて認識された。平成XX年XX月XX日にヒトもしくは動物の狂犬病が疑われた、もしくは発生した自治体において、発見から検査までの初期対応が適切に行われて不必要な社会混乱を招かないことを願う。
参考資料等
・感染症予防必携(第2版), 狂犬病 Rabies (4類−全数・狂), p.102-106
・Hemachudha T and Wacharapluesadee S, Clin Infect Dis 39: 1085-1086, 2004
・WHO Expert Consultation on Rabies, First report, Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO Technical Report Series, No.931)
・Rabies, Eds: Jackson AC and Wunner WH, Academic Press, Elsevier, 2002
国立感染症研究所
獣医科学部 井上 智 山田章雄
ウイルス第一部 森本金次郎 倉根一郎
感染病理部 飛梅 実 佐多徹太郎
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

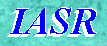
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る