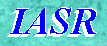2006年11月に国内で36年ぶりに相次いで2例の狂犬病事例が発生した。以下に横浜市の事例について報告する。
症例:65歳、男性。
主訴:発熱、嚥下困難。
現病歴:
2004年より貿易業のためフィリピンに滞在。2006年8月末にマニラ近郊で友人の飼いイヌに右手首を咬まれた。曝露前も曝露後も狂犬病ワクチン接種を受けなかった。10月22日仕事の都合で一時帰国した。11月15日より倦怠感と右肩甲骨痛が出現した。市販の感冒薬を内服していたが、11月18日より飲水が困難となり、11月19日に前医救急外来を受診した。感冒と診断され、解熱・鎮痛薬の処方を受けた。11月20日発熱、呼吸苦が出現し、再度前医を受診した。興奮状態にあり、精神疾患も疑われたが、海外でのイヌへの曝露歴から狂犬病を疑われ当院に紹介入院した。
既往歴:特記すべき事項なし。
生活歴:貿易業。アルコール機会飲酒。違法薬物使用歴なし。
入院時現症:心拍数 120/分、呼吸数32/分、血圧 145/90mmHg、体温38.6℃、瞳孔 3mm/3mm、意識清明、易興奮性、恐水・恐風発作あり、四肢麻痺なし、知覚障害なし、四肢末梢冷感あり、項部硬直なし、右手首に約2cmの線状の咬傷痕あり。
検査所見
血液ガス(room air):pH 7.622、PCO2 15.1Torr、PO2 105Torr、HCO3 15.8mEq/l 。血液検査:WBC 22,810/μl、Hb 16.8g/dl、Plt 17.5万/μl、生化学検査:T-Bil 3.8mg/dl 、γ-GTP 132IU/l 、AST 253 IU/l、ALT 45 IU/l 、UA 11.1mg/dl、LDH 592IU/l、TP 8.7g/dl、BUN 40.4mg/dl、Cre 1.56mg/dl、Na 145mEq/l、K 2.5mEq/l、Ca 10.2mg/dl、CK 10,130IU/l、Glu 113mg/dl、CRP 2.7mg/dl、マラリア原虫抗原検査・塗抹検査陰性。髄液検査:初圧 30mmH2O、細胞数(多核球 5/3、単核球 11/3)、蛋白 36 mg/dl、Glu 82mg/dl。髄液・血液培養陰性。尿検査:異常なし。心電図所見:洞調律。胸部単純写真:異常なし。頭部CT、MRI:異常なし。
入院後経過
発熱、恐水・恐風発作、易興奮性、イヌへの曝露歴から狂犬病が疑われたが、極めて稀な疾患であり、脳炎、敗血症、破傷風、心因性反応等との鑑別が必要であった。初期治療としてacyclovir、ceftriaxone、抗破傷風ヒト免疫グロブリンの静脈内投与を行った。狂犬病の診断については血清、尿、唾液、髄液を検体として国立感染症研究所に依頼した。全身状態の急激な悪化も予測されるためICU管理としたが、わずかな空調の風量で恐風発作が出現した。本人・家族に「狂犬病の疑いがあり、その際には突然の呼吸停止の危険があること、苦痛を除くためには鎮静・人工呼吸器管理が望ましいこと」を伝え、同意取得の上、人工呼吸器管理とした。翌11月21日に唾液のRT-PCRにより狂犬病ウイルス遺伝子が検出され、狂犬病と確定診断した。acyclovir、ceftriaxoneを中止した。11月23日家族に救命の可能性はほぼないことを説明、付き添い希望により内科系病棟個室に転棟した。体位変換などの刺激で一過性の血圧低下が起こるようになった。曝露後予防なしで生存し得た症例が1例のみ報告されており1)、家族に説明同意取得の上、倫理委員会の承認を得てribavirinとamantadineを使用した。11月25日流涎量が著しく増えた。11月26日肝機能障害が進行したため、ribavirinを中止した。12月1日黄色ブドウ球菌(後日MSSAと判明)による右肺炎が出現、vancomycin投与を開始した。12月2日腎機能が悪化し、乏尿となった。カテコラミン製剤で血圧の調節を行ったが数分ごとに血圧60台〜 200台、脈拍30台〜180台に変動した。家族と相談した結果、腎不全に対して透析を行わない方針とした。12月7日多臓器不全により永眠した。剖検後の免疫染色およびRT-PCR法により、脳および全身の神経線維に狂犬病ウイルスが認められた。
感染予防策
2006年5月に改訂されたCDCの医療従事者用Q&A2)を参考に実施した。これまでに狂犬病患者から医療従事者への感染の報告はないが、粘膜・傷のある皮膚に対し、ウイルスを含む唾液等が付着した場合は感染の可能性を否定できず、特に挿管・吸引等の際には確実に防護するよう勧められている。当院では当初から狂犬病の可能性が指摘されていたため、初診時からサージカルマスク、手袋着用の注意を喚起、挿管時にはゴーグルを着用した、入院翌日には院内感染対策委員会が感染予防策を作成し、状況確認ラウンドを行った。入室時はシールド付きサージカルマスクと手袋を着用、吸引時には閉鎖式吸引チューブを用いた。患者との接触者調査を以下のように行った。「患者の唾液等の体液が粘膜・傷のある皮膚に付着した」職員は申告するよう院内通知を出し、感染症部医師により感染リスクがあったと判断されたもの、および本人の希望があった場合には曝露後予防を行った。
考 察
狂犬病はまれな疾患であり、診断には直前に発生した京都の事例が参考になった。本疾患は致命的な疾患であり、確定診断後は本人の苦痛緩和と家族への精神的支援に治療の重点を置いた。職員の感染予防策については2006年5月に改訂されたCDC の狂犬病に関するQ&Aを参考に実施し、特に混乱は生じなかった。
文 献
1) Willoughby RE Jr et al ., N Engl J M 352: 2508-2514, 2005
2) CDC, Rabies Questions & Answers, Rabies prevention and control: Healthcare settings - Updated May 10, 2006
| 横浜市立市民病院感染症部 | 高橋華子 | 相楽裕子 |
| 同管理部感染管理担当 | 藤田せつ子 | |
| 同病理部 | 林 宏行 | |
| 同検査部 | 吉田幸子 | |
| 国立感染症研究所獣医科学部 | 井上 智 | |
| 同感染病理部 | 佐多徹太郎 |
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)