1990年前半より本邦ではインフルエンザの流行期間中に脳炎・脳症の発生報告がみられるようになり、1998年、1999年にはインフルエンザの急激な増加と急性脳炎・脳症の増加の一致がサーベイランス上からも明瞭に見られるようになった(IASR 19:272-273, 1998 & 20: 289-290, 2000)。その後「インフルエンザの臨床経過中に発生する脳炎・脳症の疫学および病態に関する研究班」(班長:森島恒雄・岡山大学大学院医歯学総合研究科小児科学教授)が発足し、同研究班が中心となってインフルエンザ脳症発生のメカニズムの解明、危険因子の推定、治療法の開発等について、現在に至るまで様々な研究が行われてきてきた。米国でも、近年インフルエンザ脳症の報告がなされ、調査が行われている(CDC, MMWR, 52(49): 1197-1202, 2003)。
2003/04シーズンのインフルエンザ脳症の全国調査は森島班が中心となって、都道府県からの一次調査の報告に基づいて二次調査を依頼または実施したものである。
2003/04シーズンは分離株数から見た流行ウイルスではAH3型が90%以上を占め、その他の多くがB型の流行であったが、過去10シーズンの流行と比較して中規模の流行にとどまった(IASR 25: 285-286, 2004)(図1)。インフルエンザ脳症の調査では、一次調査、二次調査合わせて99例の報告が得られたが、これは2002/03シーズンの160例と比べて減少した。地域別にみると、関東、関西、中部地方に多く、東北、九州、中国・四国は少なく、北海道からの報告はなかった。発症者を年齢別にみると、1歳にピークがあり、1歳以降6歳までは順次発生数が低下しているが、7歳以上の症例は例年に比して多かった。ウイルス型別では、「A型」66%、「A・B両型」25%、「B型」5%、「型不明」4%であった。脳症の予後であるが、「後遺症なし」38%、「後遺症あり」19%、「経過観察中」33%、「死亡」10%であり、致命率は2000/01シーズンよりもさらに低下していた。
2003年11月の感染症法改正に伴って、急性脳炎はこれまでの基幹定点報告疾患から5類全数把握対象疾患に変更となった。さらに2004年3月、この急性脳炎には、インフルエンザ脳症も含まれることが明確になった(IASR 25: 301, 2004)。
2004/05シーズンは流行の開始時期が2004年第3週と遅く、そのピークも第9週と例年よりも4週間以上遅かったが、流行のピーク、規模ともに現在のインフルエンザ定点によるサーベイランスが開始された1999/2000シーズン以降最も大きかった(図1)。分離株数から見た流行ウイルスは、B型が56%、AH3型41%、AH1型3.1%であり、B型が50%を超えたのは1997年以来である。急性脳炎のサーベイランスとして全国の自治体から報告されたインフルエンザ脳症の発生報告数はこれまでで51例であり、型別では「B型」57%、「A型」31%例、「A・B両型」6%、「型不明」6%であった。B型の流行状況を反映してB型のインフルエンザウイルス感染に起因する脳症が多く、また致命率は16%であった。しかしながら、この報告には30歳以上の症例が7例含まれており、また幼児の例であっても経過からは熱性痙攣の可能性が高いと考えざるを得ないものも含まれている。今後研究班に寄せられた情報や調査結果によって、報告数や致命率等については、数値が変動する可能性が高い。
インフルエンザ脳症の全国調査は、2003/04シーズンまでは研究班が厚生労働省の支援を受けて実施してきた。先述した通り、2004/05シーズンからは5類疾患となった急性脳炎のサーベイランスに組み込まれる形で、医師は経験したインフルエンザ脳症を含む、急性脳炎・脳症と診断したすべての症例を保健所に届出なければならないこととなった。これはインフルエンザ脳症の発生をできる限り漏れることなく把握するためには非常に有用であると思われる。
今後ともインフルエンザ脳症の発生動向を追求することは、本症の病態や疫学状況を解明し、発生の予防や予後の改善に繋げていく上において極めて重要である。そのためには漏れなくインフルエンザ脳症の発生報告を集積し、しかもその報告の精度を高めていくことが大きな課題である。
国立感染症研究所・感染症情報センター 安井良則 上野久美
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

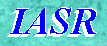
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る