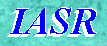
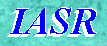
The Topic of This Month Vol.26 No.3(No.301)
百日咳菌は好気性のグラム陰性短桿菌で、百日咳毒素(PT)、繊維状赤血球凝集素(FHA)、パータクチン(PRN)、アデニル酸シクラーゼ毒素(ACT)などの病原因子が同定されている。百日咳菌は患者の上気道分泌物の飛沫などにより経気道的に伝播され、その感染力は極めて強い。わが国では、1981年から精製抗原(不活化PTおよびFHAが主)を含むジフテリア・百日咳・破傷風三種混合(DPT)ワクチンが使われている。接種開始年齢は初め集団接種・2歳以上が原則であったが、1994年の予防接種法改正で1995年4月からは個別接種・3カ月以上となった。数社のワクチンには微量のゼラチンが含まれていたが、抗ゼラチンIgE抗体を産生させることが判り(Sakaguchi M & Inouye S, Jpn J Infect Dis 53: 189-195, 2000)、1999年までに全社のDPTワクチンがゼラチン無添加に改良された。
百日咳患者発生状況:百日咳は感染症法に基づく感染症発生動向調査の5類感染症として全国約3,000の小児科定点から毎週患者数が報告される。1950〜70年まで百日咳は約4年ごとの流行を繰り返していたが、その後流行は徐々に小さくなり、1982〜83年、1986年、1990〜91年にわずかな患者数の増加が認められたが(IASR 18: 101-102, 1997参照)、1997年以降は流行を示す明確なピークはなくなった(図1)。
2000〜04年の患者発生状況を都道府県別にみると、2000年には定点当たり患者報告数が2.0以上の都道府県が11県認められたが、2001年以降では山形県、徳島県、栃木県のみとなった(図2)。このことから、都道府県をまたぐような百日咳流行はすでに消失していると言える。
図3に1982〜2004年における百日咳患者の年齢群別報告数(年間定点当たり)を示した。DPTワクチン導入後それまで患者の約4割を占めていた1〜4歳の患者が大きく減少した。0歳の患者も減少したが、まだ4年の周期性が残っている。また2004年にはわずかながら各年齢群で増加が示された。なお、2000年以降、0歳が1〜4歳の患者数を上回っているが、1999年の感染症法施行以降、定点を小児科中心の医療機関に変更したことから他の疾患でも同様に低年齢の患者割合の増加がみられている(IASR 25: 318-320, 2004参照)。
百日咳抗体保有状況:2003年度の感染症流行予測調査により一般健康者の百日咳ELISA抗体保有状況が調査された(なお、2003年度は初めて小児のみならず成人を含む全年齢層での調査となった)。ワクチンの主成分であり抗原性の異なるPTとFHAに対する抗体が発症および感染防御に働くと考えられている。また、百日咳患児の回復期血清の抗体価下限値から抗体価10単位(EU/ml)が感染防御レベルと推定されていることから、ここではPTとFHAの抗体価10単位以上の保有率について考察を行う。年齢群別抗体保有状況の調査では、抗PT抗体では45〜49歳群で28%と最小値を示したが、他の年齢群での保有率は41〜60%であり、年齢による大きな差は認められなかった(図4)。一方、抗FHA抗体では25〜44歳の年齢層でやや低い(51〜57%)が、他の年齢群では高いレベル(71〜91%)で抗体を保有していることが示された。25〜29歳の年齢群は1975年のワクチン接種一時中止〜1981年のDPTワクチン導入までの接種率が低かった時期と符合する。また、30代〜40代前半の年齢層は全菌体ワクチンの接種時期に相当する。
ワクチン接種歴別の抗体保有状況を見ると、抗PT抗体および抗FHA抗体ともに抗体価10単位以上の保有率は追加接種による影響を受けていないことが示された(図5)。ワクチン未接種群では年齢とともに抗PT抗体と抗FHA抗体保有率の上昇が認められ、患者数の激減した現在でも百日咳菌は市中を循環しており、ワクチン未接種児が感染することを示唆している。抗PT抗体、抗FHA抗体ともに1〜16歳における保有率はほぼ一定であり、1995年以降差が認められなかったことから(図6)、現行ワクチンの品質に変化は起きていないと考えられる。
現在の問題点:わが国では百日咳の流行はすでに無くなったが、産科や小児病棟などでの小規模な集団発生(院内感染)(本号4ページ参照)や家族内感染(本号4ページ&6ページ参照)が散見される。典型的な症状を示さない年長児や成人が百日咳と診断されず、感染源となる場合が多いと考えられる。百日咳の確定診断に必要な百日咳菌の分離率は低く、また、抗体検出は時間を要するため、臨床現場では症状による臨床診断が主に行われている。PCRによる遺伝子診断も研究室レベルでは行われているものの、まだ特異性と検出感度は十分とは言えない。実際には百日咳と確定診断されず報告されない散発例や集団発生事例が多数潜在していると考えられる。今後、迅速かつ簡便な遺伝子診断法等の開発が必要であろう。
予防接種法改正で1995年にワクチン接種開始年齢が早くなったことにより1〜4歳の患者数は減少した。しかし、0歳児の患者の減少は最近止まっていることから、生後3カ月になったらできるだけ早期にワクチン接種を受けることが望まれる。これはワクチン接種歴と罹患率の関係からも明らかである(本号7ページ参照)。しかし、高いワクチン接種率を維持する米国などで近年患者数の増加が認められており、百日咳は再興感染症として位置付けられている(本号9ページ参照)。海外での百日咳の再興原因は明らかとなっていないが、流行株の変異(本号3ページ参照)や青年層での患者増加(本号6ページ参照)などが認められている。また、米国では少数例ながらマクロライド耐性百日咳菌の出現が確認されている(本号8ページ参照)。
患者数が激減した現在、定点サーベイランスでは定点のない地域の小流行を探知することが困難となっている。正確な患者発生動向を把握するためには、今後、例えば全数報告のようなサーベイランスシステムの構築が必要となろう。わが国でも百日咳菌の薬剤耐性株の出現や、抗体価の減衰した成人の感染によって百日咳患者数が増加する可能性は否定できないため、病原体サーベイランスを強化して菌分離と解析を積極的に行う必要がある。
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)
