世界中どこでも、先進工業国であると発展途上国であるとを問わず、生後5年以内に、ほとんどすべての小児がロタウイルスに感染する。この感染は、わが国をはじめとする先進工業国において、小児科外来を受診する下痢症患者の15〜30%、同じく入院患者の40〜60%がロタウイルスに起因するという大きな疾病負担となっている。わが国では就学前小児がロタウイルスに起因する下痢症により、小児科外来を受診するリスクは50%(2人に1人)と推定され、総患者数は年間約80万人に及ぶと推定される。米国では、生後5年以内に8人に1人が外来受診、70人に1人がロタウイルス下痢症で入院し、年間入院数は約5万人と推定されている。一方、途上国では、同じロタウイルス感染が、約 200人に1人の死亡リスクと年間約66万人の小児死亡の直接原因という大きな疾病負担となっている。
ロタウイルス感染症制御の世界戦略を理解するポイントは以下の3点である。第1は、上述のごとく、途上国、先進国ともに、ロタウイルス感染に起因する大きな疾病負担があること。第2に、細菌性腸管感染症と異なり、一般的衛生状態の改善や上下水道の整備によってロタウイルスの自然感染を減らすことは不可能であること。第3に、疾病負担中最大のものである、死亡や入院を 100%近く予防できるワクチンが事実上完成していること、である。このような事情により、ワクチンと予防接種に関する世界同盟Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)では、ロタウイルスワクチンによる下痢症対策は、手の届くところにぶら下がっている果実をもぎとるだけのことであり、現在のトッププライオリティーであるとして、政府、民間団体、製薬企業などのパートナーシップを要請している。
最初に実用化されたロタウイルスワクチンはサルロタウイルス(RRV株)を親株にし、3つの組換え体ウイルス(血清型G1、G2、G4)と親株自身(血清型G3)を混合した4価ワクチン(RotaShield)であった。RotaShieldはフィンランド、米国、ベネズエラで行われた大規模な第III相野外試験で重症下痢症に対して80〜90%の有効率を示し、米国と欧州連合加盟国で認可された。RotaShieldは、ロタウイルスワクチンの目的が重症下痢症を予防することにあることを確立し、この目標を達成することが弱毒生ワクチンにより可能であることを示した。米国では発売から10カ月間でバースコホートの25%に相当する約100万人の乳児が投与を受けた。しかし、RotaShieldは、被接種者11,000人に1人と推定される腸重積症を副反応として起こす疑いにより市場から撤収された。最近になって、米国NIHの研究者がデータの再解析を行い、RotaShieldが腸重積症発症のリスクになるのは、生後3〜7カ月に接種されたときであると主張している。そこで、生後0〜4週に初回投与,4〜8週に第2回投与を行うことにより、腸重積症発症のリスクを回避しつつ、腸管での増殖力の強いRRV 株の特徴を生かして、最貧国の乳児においても有効な免疫を獲得させようという努力が開始されている。この一環として、米国NIHはRRV-TV(RotaShieldはWyeth 社の商品名であった)を米国のバイオテク会社であるBIOVIRxに再ライセンスした。このプログラムがうまく行けば、世界のいずれかの地で、RRV-TVはよみがえる可能性がある(表1)。
現在、もっとも注目されているロタウイルスワクチンは、GlaxoSmithKline(GSK)社が開発したRotarixとMerck社が開発したRotaTeqであり、いずれのワクチンも、腸重積症発症のリスクが増加するかどうかという安全性試験を兼ねた第III相試験を6万〜7万人規模で展開している。このさなか、2004年7月にはRotarixがメキシコで認可された。順調に行けば、RotaTeqも2005年内に米国で認可されると見込まれている。
RotarixとRotaTeqは弱毒生ワクチンという点では似ているが、非常に異なる性格をもっている。Rotarixは、ヒトロタウイルス89-12株を培養細胞で33代継代するというオーソドックスな方法で弱毒化し、プラーク純化した血清型G1P1A[8]の単価ワクチンである。Rotarixは単価ワクチンであるため、流行株がG1以外の血清型、とくにG2である場合に果たして期待される効果を示すことができるかどうかに関心が集まっている。現在までの野外試験では,血清型G1とG9のウイルス株が流行している状況下で、重症下痢症に対し85%、すべてのロタウイルス下痢症に対し72%の有効性を示すことが確認されている。
一方、RotaTeqはウシロタウイルスWC3株を親株にし、防御に重要な中和抗体を惹起する血清型G1〜G4のVP7とP1A[8]のVP4蛋白をコードする遺伝子をヒトロタウイルスからとった5価の遺伝子分節組換え体ワクチンである。このワクチンは防御免疫がG血清型に強く依存するという仮説に基づいている。RotaTeqはロタウイルス下痢症の発症を約70%、また重症下痢症を完全に予防するという野外試験の結果が得られている。
ロタウイルスは1973年に発見されて以来、30余年が経過するが、これからの5年間がロタウイルス感染症制御のうえで、もっとも重要な時期になる。それはここで紹介した3つのワクチンが、米国や欧州連合はもとより、ワクチンをもっとも必要とする途上国に導入され、ロタウイルス感染症による世界の疾病負担の様相を一変させるというゴールに向かっての努力が期待されるからである。
この世界的な取り組みに対する障害要因は次の3つである。第1に、腸重積症の問題。新しいワクチンに再び腸重積症の問題が起ったとき、それは、あらゆる弱毒生ワクチンの開発に事実上の終止符を打つことになり、ロタウイルスワクチンを市場に出せる能力のある世界規模での製薬企業の開発意欲を消滅させるであろう。第2に、拡大し変貌するロタウイルスの血清型と種間伝播の問題。ロタウイルスの主要な血清型がG1〜G4でカバーできた時代は終焉を迎えつつある。アジアやアフリカ、南米の熱帯地では、種間伝播に起因すると思われる、G9、G8、G5などの血清型の相対頻度が増加し、認可を待っているワクチンへの潜在的脅威となっている。第3に、最貧国におけるワクチンテイクの問題。ここで紹介する3つのワクチンはもとより、開発中のワクチンのほとんどは弱毒生ワクチンである。弱毒生ワクチンは不活化ワクチンと異なり、接種量そのものでは有効な免疫を惹起できない。接種されたウイルスが腸管内で、しかるべき量にまで、かつ、しかるべき量を超えることなく増殖して初めて、有効な免疫を付与できる。恒常的にさまざまな腸管感染症にさらされ、かつ、低栄養状態にある最貧国の乳児に、とりわけ、腸重積症の発生を防ぐため、生後0〜4週の時期に初回接種を行ったとして、ワクチンがテイクし、有効な免疫が惹起できるのかという問題がある。最貧国においてワクチンのテイク率が低ければ、われわれは所期の目的を達成することができない。
このようなロタウイルスワクチンをとりまく現状に対し、わが国にはいかなる役割が期待されるのであろうか。わが国の研究機関にはサーベイランスや野外流行ウイルス株の解析に関する優れた能力があり、これを国際的ネットワークの中で活用するという貢献が期待される。国内での発生動向調査体制を引き続き充実させていくことも重要である。最近、感染症情報センターが地方衛生研究所からのロタウイルスのG血清型情報を受け入れ、これを情報として発信できる体制を整備したことは特筆される。わが国の研究者や公衆衛生政策担当者がロタウイルス感染症を解決済みの問題として等閑視すれば、国際的協調努力の中で貢献できないばかりか、先進国においてはワクチンによりロタウイルス下痢症で入院する小児がいなくなっても、わが国の小児にはロタウイルスワクチンを利用するというオプションがないということになりかねない。このような事態に至らせないよう関心を喚起することはわれわれの社会的責務であろう。
秋田大学医学部・感染制御学 中込とよ子
長崎大学大学院・病態分子疫学 中込 治
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

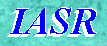
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る