細菌性髄膜炎は、 1999年4月から施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において基幹病院定点届け出の4類感染症に分類されている。抗菌薬療法の発達した今日でも小児の重症感染症として極めて重要な疾患である。
原因菌として分離頻度の高い肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae )やインフルエンザ菌(Haemophilus influenzae )の耐性化が近年問題となっており、 従来標準的な治療法とされてきたampicillin(ABPC)+cefotaxime(CTX)またはceftriaxone(CTRX)では治療に失敗する例も増加し、 深刻な問題となっている。
小児細菌性髄膜炎の全国調査は、 既に小林(1966〜1978年)1)、 藤井(1979〜1984年)2-5)、 岩田(1985〜1997年)6)が継続的に実施しており、 今回我々はアンケートによる1997年以降の全国調査を実施した。
2000年8月に全国 277施設の小児科にアンケート調査用紙を送付し、 1997年7月〜2000年6月までの3年間の小児細菌性髄膜炎(症例の定義は髄液所見での細胞数増加と菌の検出)について回答を求めた。回答率は49%で、 101施設から428例の症例が報告された。
1.症例数(図1)
小児細菌性髄膜炎の症例数は1997年7〜12月86例、 1998年117例、 1999年136例、 2000年1〜6月89例で、 年間小児科入院1,000人当たりの症例数は1.1〜1.7人、 男女比は男児248例、 女児180例(1.4:1)で、 死亡は男児10例(4%)、 女児4例(2%)であり、 死亡率に男女差は見られなかった(p= 0.3)。
2.年齢分布(図2)
428例の年齢分布は男女ともに1歳未満が最も多く、 年齢が高くなるとともに発生数は少なくなる。1歳未満の200例については1月未満が多く、 1月未満の48例では生後7日以内が多いという結果であった。
3.年度別原因菌検出数(図3)
いずれの年度も原因菌としてH. influenzae が最も多く、 S. pneumoniae が続いた。原因菌の変遷を1966年から同様の調査を実施した論文からまとめると、 H. influenzae はS. pneumoniae を含む他の菌種に比べて明らかに増加の傾向を示していた(p= 0.003)。
4.原因菌別発症年齢分布(p.2 特集図4参照)
分離数の多い上位4菌種について年齢分布を調査した。B群レンサ球菌(GBS)は3年間で25株が分離されていたが、 2株を除き4カ月以下の小児であった。大腸菌(Escherichia coli )は24株で、 全例4カ月以下の乳児であった。H. influenzae は最も多く204株で、 1カ月(2株)、 5歳(2株)、 6歳(4株)、 8歳(2株)の計10株を除く194株が3カ月〜4歳に分布し、 特に2歳未満に多いとの結果であった。一方、 S. pneumoniae は87株で、 2株を除いて2カ月〜10歳に分布しており、 H. influenzae に比べて5歳以上の年長児にも患者がみられた。
5.分離H. influenzae 、 S. pneumoniae の薬剤感受性(図4)
各施設で実施した薬剤感受性検査は、 H. influenzae はABPCに対する感受性の結果で、 S. pneumoniae はペニシリンに対する感受性で分類した。H. influenzae は25%、 S. pneumoniae は39%が耐性であった。
送付されたH. influenzae 、 S. pneumoniae の薬剤感受性成績ではH. influenzae に対してはCTRXやCTXが有効でありmeropenem(MEPM)が続く。S. pneumoniae に対してはカルバペネム系のpanipenem/betamipron(PAPM/BP)やMEPMが有効であり、 vancomycin(VCM)が続く。S. pneumoniae は、 小児細菌性髄膜炎の第一選択薬であったABPCやCTX、 CTRXに対しては耐性の傾向にあり、 効果が期待しにくいという結果であった。
6.菌種別の予後(図5)
調査表から菌種別に死亡、 後遺症あり、 後遺症なしにわけて解析を行ったところ、 肺炎球菌性髄膜炎では他の菌種による髄膜炎に比べて後遺症ありおよび死亡の症例が多いとの結果であった(p <0.001)。後遺症としては硬膜下水腫、 脳膿瘍、 水頭症、 けいれん、 難聴、 麻痺、 精神発達遅延が多く見られた。
以上の結果から、 今後は薬剤耐性のH. influenzae やS. pneumoniae の増加が懸念され、 有効な薬剤の開発が望まれるとともに、 わが国においても海外で既にその効果が確認されているH. influenzae 、 S. pneumoniae のワクチンの接種を真剣に考えていく必要があると考えられた。
参考文献
1)小林 裕他、 Jap. J. Antibiotics; 2: 795-805, 1979
2)藤井良知他、 感染症学雑誌; 60: 592-601, 1986
3)藤井良知他、 感染症学雑誌; 61: 849-857, 1987
4)藤井良知他、 Jap. J. Antibiotics ;40: 284-294, 1987
5)藤井良知他、 Jap. J. Antibiotics; 40: 812-822, 1987
6)岩田 敏、 小児感染免疫; 10: 139-146, 1987
北里大学医学部感染症学 砂川慶介
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

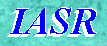
 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る