 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る
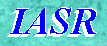
献血者におけるHIV感染状況
(Vol.21 p 140-141)
欧米諸国では、献血血液中のHIV抗体陽性率は年々減少するか、低いレベルで安定しているが、わが国では、これまで一貫して陽性率が増加し続けており、1999年には、ついに10万検体中1を超え(正確には1.02)、西欧諸国の中央値(1997年段階で10万人あたり1.05)にほぼ等しくなった。周知のように、HIVの流行は、日本と西欧とでは、大きく異なっている。たとえば、表1は、日本と献血検体陽性率の比較的近い、英国と流行の指標を比較したものである。AIDS患者の人口比を見ても、妊婦の感染率を見ても、両国間に著しい違いがあることが一見して明らかである。従って、献血検体陽性率が等しいというのは、実は奇妙な現象であるといわねばならない。この違いを数量化して比較するために、献血血液のHIV抗体陽性率を、国連合同エイズ計画(UNAIDS)が発表している1997年の推定国民感染率で除した指数として、すなわち、その国の流行度に相対化した指数として比較したのが表2である。西欧諸国の指数の中央値は、7.0(4分位値=3.7と10.2)であるのに対し、日本の指数は90と、その差は13倍にもなる。わが国の献血血液のHIV抗体陽性率は、HIVの流行規模に比して異常であると言うより他はない。
献血血液のHIV抗体陽性率が高いことは、いわゆるウィンドウ期の血液による輸血感染の危険が高い可能性を示唆している。そこで、1997年の日本全国のHIV抗体陽性の献血血液52検体の約60%にあたる32サンプルを入手して、そのHIV抗体価を検討した。市販のパネル血清を用いた基礎検討から、PA法(粒子凝集法)で1,000倍希釈未満でしか抗体検出ができない血清を“抗体上昇早期”(抗体出現後17日以内)であるとすると、32検体中3検体(9.4%)がそのような“抗体上昇早期”の検体であることが明らかとなった。抗体上昇早期の直前にほぼ同じ長さ(22日)の感染性ウィンドウ期が存在するため、1997年の献血血液には、感染性ウィンドウ期の血液が混入する危険があったということになる。
それでは、西欧に比して、なぜこのように献血にHIV陽性者が集中するのであろうか。その原因としては、(1)問診によるスクリーニングが十分に機能していない、(2)献血を検査目的に利用する人がいる、(3)献血者を構成する一部のグループ[特に男性間で性行為を行う人々(以下、MSM)]の中に、HIV感染が流行していることなどが考えられる。それぞれの寄与を示唆するデータが得られていることから、実際には、これらが複合したものと見るべきであろう。これに照らせば、西欧では、薬物乱用者やMSMにおけるHIV流行はわが国より依然遥かに高率であるから、西欧で抗体陽性率が低率にとどまっているのは、それらのグループが献血を行っていない、問診が機能している、検査目的の献血者が少ないなどの理由のいずれか、あるいはそれらすべてによる可能性があるが、わが国の対策の参考とする上からも、それを裏付ける調査研究が求められる。献血血液の安全性を高めるために、日赤はHIVを含めたNAT(核酸増幅法)の導入に踏み切ったが、それでも、感染性ウィンドウ期は半分に縮まるに過ぎない。これが大変な努力であり進歩であるとはいえ、もし、それが検査目的の献血者を惹きつける効果(マグネット効果)を持つことになれば、折角の努力が相殺されるばかりか、その程度によっては逆効果にさえなりかねないのである。献血を検査目的に利用する必要がないよう、エイズ予防対策指針に記されている「利便性の高い場所と時間帯を配慮した検査」の実施を具体化していくことが急務であると考えられる。
京都大学大学院医学研究科国際保健学 木原正博
神奈川県衛生研究所ウイルス部 今井光信
東京女子医大輸血科 清水 勝
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

