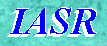
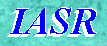
The Topic of This Month Vol.20 No.5(No.231)
食中毒統計:カンピロバクターは食中毒起因菌としてサルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌に次いで発生頻度が高い。全国におけるカンピロバクター食中毒患者数は、1985年に9,497人と急増したが、その後1993年には948人まで減少した。しかし1994年以降は再び増加し、1,500〜2,600人で推移している(図1)。一方、事件数は1995年まで50件以下であったが、1996年65件から1997年257件、1998年553件と大きく増加している。これは、1997年頃より一部の県で患者数1名の発生をすべて食中毒事件として届け出るようになったことが大きく影響している。
地研・保健所集計:1983〜1998年の年別カンピロバクター検出報告数を表1に示した。食中毒統計と同様1985年に2,810とピークとなった後、1993年には599まで減少した。しかし1994年以降は約700〜1,300で推移している(1980年代に比べ半数以下)。1995〜1998年の検出報告のうち菌種まで報告された割合は87%で、種別された中ではC. jejuniが全体の約97%を占め、C. coliは非常に少なかった。
1995〜1998年の月別カンピロバクター検出報告数を図2aに示した。1994年以前と同様4〜7月に検出報告数のピークがみられ、この傾向は英国や米国でのカンピロバクター腸炎発生動向とも類似している(CDSC、CDR、Vol.8、No.24、p.211参照)。
1997年6月の大きなピークは、奈良県内の小学校で発生した給食を原因食とする大規模な食中毒によるものである(本月報Vol.18、No.11参照)。
1993〜1998年に地研・保健所から報告されたカンピロバクター食中毒集団発生は169件であった(表2、1992年以前の報告については本月報Vol.14、No.7参照)。発生規模別では、患者数100人以上が20件(12%)、50〜99人が18件(11%)、10〜49人が80件(47%)、2〜9人が51件(30%)であった。従来ほとんど報告のなかったC. coliを起因菌とする事件が1996年以降5件報告されている。原因の判明した事件は169件中49件(29%)で、その内訳は、鶏肉関連によるものが39件と最も多く、飲料水3件、給食7件であった。1996年に検食の保存期間が2週間に延長されたにもかかわらず、原因食品の判明率は1997、1998年になっても相変わらず低い。しかし、地研・保健所で実施された食品等の検査結果の報告(表3)ではC. jejuni/coliは鶏肉および食鳥処理施設のふきとり材料から高頻度に分離されており、カンピロバクター食中毒が本菌に汚染された鶏肉およびその二次汚染に起因することを裏付けている(本号4ページ参照)。
地研のカンピロバクターレファレンスセンターによって、1996年6月〜1998年5月までに型別されたC.jejuniは、集団食中毒51事例由来590株、散発下痢症由来1,163株で、前者ではLIO 7型が19事例(37%)209株と最も多く、次いでLIO 2型が8事例(16%)43株であり、後者ではLIO 4型が145株(20%)と最も多く、LIO 7型63株(8.6%)、LIO 1型62株(8.5%)、LIO 2型52株(7.1%)などがこれに続いている(本号3ぺージ参照)。
都市立伝染病院集計:1995〜1998年にカンピロバクター腸炎で入院した患者214例の年齢分布をみると(表4)、従来の報告と同様に0〜9歳が35%と最も多く、次いで20〜29歳が33%、10〜19歳が17%で、30歳以上は少なかった。また20〜29歳では、その63%が海外で感染した輸入例であった。性別では男性の方がやや多かった。入院患者では例数が少ないため季節性は明確ではない(図2b)。入院患者の便の性状は水様便が90%で、さらに血便が48%、粘液便が25%にみられた。患者の87%に腹痛、38%に嘔吐がみられ、最高体温は平均38.3℃であった。
都市立伝染病院で実施したC. jejuniの薬剤感受性試験の結果では、ナリジクス酸(NA)耐性株の割合は、1995年には5.9%(2/34株)、96年37%(15/41株)、97年33%(11/33株)、98年42%(8/19株)で、増加傾向が認められた。NAに対する感受性は、C. jejuniやC. coliの同定の重要な指標であったが、NA耐性菌の増加によってカンピロバクターの種別同定が困難になってきている。またニューキノロン系抗生剤であるオフロキサシン(OFLX)耐性株も増加しており、1998年には31%(5/16株)が耐性であった。地研レファレンスセンターの検査結果でも同耐性株が増加していた(本号3ページ参照)。一方、エリスロマイシン(EM)耐性株は2/159株(1.3%)で極めて少ない。
最近、カンピロバクター腸炎後に神経疾患のギランバレー症候群、あるいはその亜型で外眼筋麻痺等を伴うフィッシャー症候群を発症した症例報告があるが(本号5ページ参照)、両者の関係およびその発生機序はいまだ十分に解明されていない。
カンピロバクタ−腸炎予防の一般的注意としては、鶏肉を調理する時には十分に加熱することのほかに、生肉を切るのに用いた包丁、まな板等の調理器具や手指を介した他の食品への二次汚染に特に気をつけることが必要である。
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

