 今月の表紙へ戻る
今月の表紙へ戻る
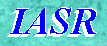
免疫抑制下で出血性膀胱炎を発症した者からのアデノウイルス35型の分離−京都市
京都市感染症サーベイランスの定点検査で、免疫抑制下の出血性膀胱炎患者尿から長期にわたりアデノウイルス35型(Ad35)が分離された。Ad35の検出は京都市では1988(昭和63)年の1件以来であり、全国的にも検出例が少ないので報告する。
患者は急性骨髄性白血病で入院中の京都市在住の7歳女児で、骨髄移植に伴う免疫抑制下にあったが、移植後25日目の1997年10月13日から血尿を伴った膀胱炎を発症し、その2週後には41℃の高熱、尿管炎、腎盂炎等の症状も呈するようになり、その後、汎血球減少に陥った。
検体は骨髄移植2日前の9月16日、膀胱炎発症直後の10月14日、1週後、3週後、5週後、7週後の計6回採取された。糞便4検体、咽頭ぬぐい液3検体、尿5検体、血液1検体の合計13検体についてウイルス検査を行った。
ウイルス分離はFL、RD-18S、Vero、HEp-2、MDCKの5種の培養細胞を使用して行ったが、Ad35は発症直後、3週後および5週後の尿から検出された。FLとRD-18Sで分離されたものが1検体、FLのみで分離されたものが2検体あり、他の細胞では分離されなかった。
細胞変性効果(CPE)はFL初代で6日目より出現し、継代したところ、2代目では1日目よりCPEが出現し、2日目には細胞全体に及んだ。一方、RD-18Sでは初代ではCPEは出現せず、盲継代した2代目6日目からCPEが現れ、3代目に継代して3日目にようやくCPEが細胞全体に及んだ。
ウイルス中和試験は国立感染症研究所より分与されたAd 1〜7、11、19、34、35、37の20単位、10単位、5単位の抗血清と、FL3代目の102 TCID50/0.1mlのウイルス液を抗原として行った。中和パターンは比較的明瞭で、抗Ad7、Ad11血清による交差反応がみられたものの、最終的にはAd35と同定できた。
Ad35が糞便、咽頭ぬぐい液、血液からは検出されず、尿からのみ検出されていることは、免疫抑制下で膀胱等で持続的なウイルス感染が起こったものと思われる。
患者は発症後、一時症状が重篤になったが、現在はリバビリン等の投与により症状は小康状態にあるが、依然免疫抑制下にあるので、今後も経過を見ながらAd35の動向を継続検査する必要があると思われる。
京都市衛生公害研究所微生物部門
唐牛良明 梅垣康弘 宇野典子
 IASRのホームページに戻る
IASRのホームページに戻る Return to the IASR HomePage(English)
Return to the IASR HomePage(English)

